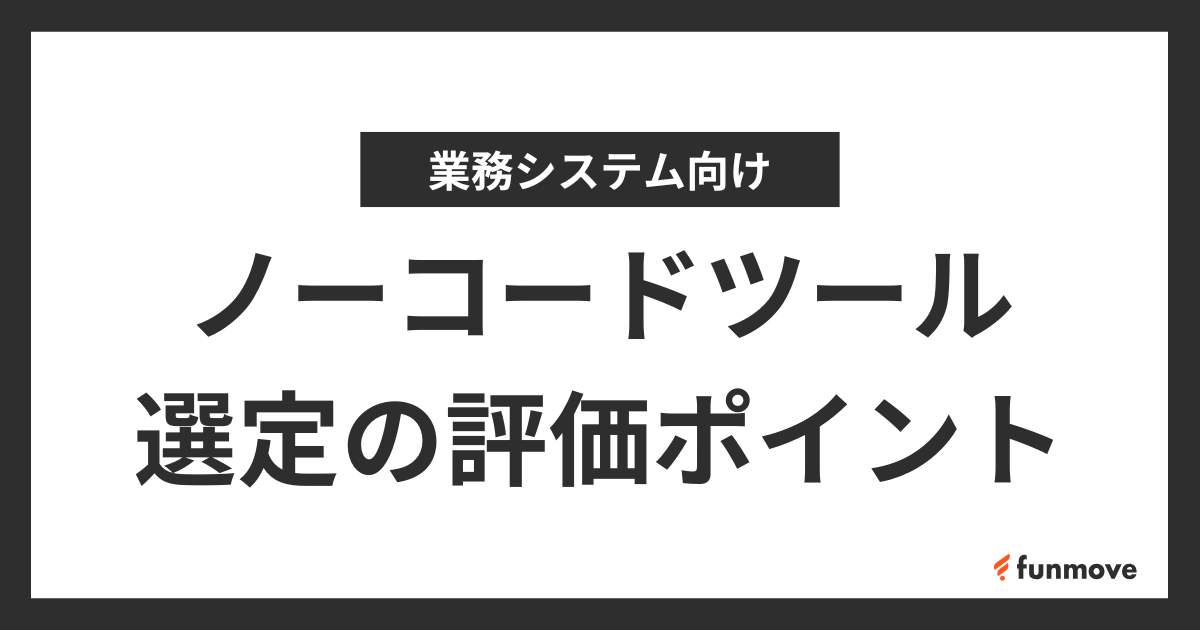
業務システム向けノーコードツールの選定に役立つ8つの評価ポイント

社内 DX の推進において、ノーコードツールの導入が増えています。
一方で、ノーコードツールを導入したいものの「ノーコードツールが多すぎて、どれが最適なのか判断ができない」というお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ノーコードツールの選定において,8 つの重要な評価ポイントを紹介します。ノーコードツール選定の参考になれば幸いです。
ノーコードツール選定における 8 つの評価ポイント
ノーコードツール選定の評価ポイントは以下の通りです。
| 評価ポイント | 概要 |
|---|---|
| 使いやすさ(UI/UX) | ・直感的な操作性 |
| 公式資料の充実度 | ・公式チュートリアルの充実度(特に初心者向け) ・関連資料の調べやすさ ・サンプルアプリやテンプレートの充実度 |
| モバイル対応性 | ・モバイル対応の有無 ・モバイル版とデスクトップ版の機能比較 |
| ノーコード機能の標準性能 | ・標準搭載のノーコード機能を用いた、システム構築力 / 汎用性 |
| 高度なカスタマイズ性能 / 方法 | ・複雑なビジネスロジックや UI の実現可能性 / 実現方法 |
| データ連携と拡張性 | ・インポート/エクスポート機能 ・API の充実度・使いやすさ ・外部システムとの連携の容易さ |
| セキュリティと権限管理 | ・アクセス権限の細やかさ ・暗号化などによるデータ保護 ・監査ログ |
| コスト | ・課金形態(初期費用、月額、ユーザー数課金など) ・追加コストの発生条件 ・スケール時のコスト予測 |
ノーコードツールを選定する際には、表面的な機能比較だけでなく、実際の業務への適合性を多角的に評価することが重要です。
各評価ポイントについて、順に掘り下げて解説します。
使いやすさ(UI/UX)
ノーコードツールの選定において、使いやすさ(UI/UX)は導入成功の鍵を握る重要な評価ポイントです。どれほど機能が豊富なツールであっても、実際の現場で直感的に使えなければ、ツールの活用は進まず、結果として投資対効果が低下します。
使いやすさを評価する際は、以下のポイントに注目しましょう。
| 評価ポイント | 確認項目 |
|---|---|
| 直感的な操作性 | ・画面レイアウトの分かりやすさ ・ドラッグ&ドロップなどの視覚的操作 ・アプリ構築・改善手順のシンプルさ |
ノーコードツールを選ぶ際は、実際に操作してみることが何よりも重要です。デモ環境やトライアル版を利用して、以下のような点を確認してみましょう。
- 初めて触れても、基本的な操作方法を素早く理解できるか
- 操作の流れに一貫性があり、迷わずに作業を進められるか
- 画面上の要素や機能が直感的に配置されているか
- 複雑な操作を簡略化する工夫(ドラッグ&ドロップなど)があるか
実際のユーザーとなる現場担当者に試用してもらい「これなら日常業務で使いこなせそうだ」と感じられるかどうかが、普及の決め手となります。
使いやすさは主観的な要素も含むため、実際に使用する部門の意見を取り入れながら評価することをお勧めします。
公式資料の充実度
学習効率と問題解決能力を大きく左右する公式資料の充実度も重要です。特に導入初期は、参照できる資料の質と量がチームの上達スピードと定着率に直結します。
公式資料の充実度を評価する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
| 評価ポイント | 確認項目 |
|---|---|
| チュートリアルの質 | ・初心者向けチュートリアルの分かりやすさ ・各レベルに即した丁寧な解説の充実度 ・動画などのマルチメディア教材の有無 |
| 関連資料の調べやすさ | ・ヘルプセンターや知識ベースの使いやすさ ・トラブルシューティングガイドの充実度 |
| サンプルとテンプレート | ・業種別・目的別のテンプレートの提供 ・実用的なサンプルアプリの提供 |
公式資料の充実度を確認する際は、下記のような点に注目すると良いでしょう。
- 初心者でもゼロから始められる基礎チュートリアルが用意されているか
- ノーコードツールの活用で困り事で役立つような、解説資料が用意されているか
- 日本語対応の資料が十分にあるか
- 実際の業務に近いテンプレートやサンプルを活用することで、開発工数を削減できそうか
豊富な公式資料は、導入後の自走力を高め、外部サポートへの依存度を下げる効果があります。特に内製化を目指す場合は、チーム全体がツールを学び、問題解決できる環境が重要です。
モバイル対応性
業務システムをモバイルデバイスで利用する予定がある場合は、ノーコードツールのモバイル対応性を評価することは重要です。特に、現場作業や外出先での利用、テレワークなど多様な働き方を想定している場合は、モバイル対応が大きな意味を持ちます。
モバイル対応性を評価する際は、以下のポイントに注目しましょう。
| 評価ポイント | 確認項目 |
|---|---|
| モバイル対応の有無 | ・スマートフォン対応の有無 ・タブレット対応の有無 ・レスポンシブデザイン(画面サイズへの自動適応)の対応状況 |
| 機能の一貫性 | ・デスクトップ版とモバイル版の機能差 ・モバイル版での使いやすさ |
モバイル対応を評価する際には、以下の点を中心に精査することをお勧めします。
- 業務で必要となる主要機能(データ登録や編集など)がモバイルでも使えるか
- モバイル版の UI は使いやすいか
特に注意すべきポイントは、デスクトップとモバイルの間での機能差です。「モバイル対応」と謳っていても、実際には閲覧機能のみなど、重要な機能が制限されていたりする場合もあります。
自社の業務シナリオを具体的に想定し、モバイルでの利用が想定される場面で必要な機能が問題なく使えることを確認しましょう。
ノーコード機能の標準性能
ノーコードツールを選ぶ際に、内製化の観点で特に重要になる評価ポイントは、標準機能だけで、どこまでシステム構築ができるかという点です。
ノーコード機能の標準性能を評価する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
| 評価ポイント | 確認項目 |
|---|---|
| 基本構築の可能性 | ・必須業務機能の実現可能性 ・プロセス自動化の範囲 |
| 汎用性の高さ | ・様々な業務要件への対応力 ・カスタマイズの自由度 ・画面デザインの自由度 |
上記を評価する方法として、使いやすさ(UI/UX)と同様に、実際に操作して確認し、標準機能の範囲を体感することをお勧めします。
標準機能の評価にあたっては、以下のようなアプローチが効果的です。
- 社内に情報システム部やDX部門がある場合は、技術的な観点からフィードバックをいただく
- 作りたいシステムの概要が決まっている場合は、ノーコードツール提供会社の営業担当者や技術担当者に実現可能性を直接質問する
- 同じノーコードツールを導入した他社事例を調査し、どのような機能を実現しているか参考にする
最終的には、ノーコードツールの標準機能と自社の業務要件とのマッチング度合いを総合的に判断することになります。
優先度の高い機能のカバー範囲を見極め、足りない部分は後述する高度なカスタマイズで補完できるかどうか検討すると良いでしょう。
高度なカスタマイズ性能 / 方法
複雑な業務要件に対応するシステムを構築するには、高度なカスタマイズ性能が重要です。業務独自の機能や処理の実現性が、長期的な活用のポイントになります。
このような背景から、カスタマイズ性能とその手段はノーコードツール選定の分かれ目と言えるでしょう。
まず、高度なカスタマイズが必要になる典型的なケースとして、以下のような状況が挙げられます。
- 業界特有の複雑なビジネスロジックを実装したい
- 既存システムと連携した独自のデータを処理したい
- 現場がより使いやすいように、独自の UI を実装したい
- etc…
上記のようなケースを実現する場合、高度なカスタマイズの代表的な方法は以下の通りです。
- ノーコードの標準機能を活用:ノーコードの標準機能が優れている場合、ノーコードで実現可能
- ローコード機能による拡張:ノーコードの標準機能の延長として、ノーコードツール上で動作するプログラムを記述することで実現可能
- プラグイン/アドオンの活用:ノーコードツール上で動作するサードパーティ製の拡張機能の活用
そのため、高度なカスタマイズ性能を評価する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
| 評価ポイント | 確認項目 |
|---|---|
| カスタマイズの方法と難易度 | ・ノーコードで実現できるカスタマイズ範囲 ・ローコード機能の有無 ・プラグイン/アドオンの提供状況 |
| カスタマイズの範囲 | ・UI/画面デザインのカスタマイズ自由度 ・ビジネスロジック(承認フロー、計算ロジック、条件分岐など)のカスタマイズ範囲 |
導入時には必要なくても、業務の発展に伴って将来的に独自の要件が生まれることは珍しくありません。だからこそ、将来を見据えたカスタマイズ性能の評価が重要です。
各ツールのカスタマイズ性能を評価する際には、「将来このような機能を追加したい場合、どのように実装できるか」といった具体的な質問をノーコードツール提供会社にしてみることをお勧めします。
データ連携と拡張性
ノーコードツールが単独で完結することは少なく、既存システムや外部サービスとのデータ連携が必要なケースが一般的です。将来の業務変化に対応できる拡張性も重要な評価ポイントになります。
データ連携と拡張性を評価する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
| 評価ポイント | 確認項目 |
|---|---|
| データの入出力機能 | ・インポート/エクスポート機能の有無 ・データ移行の容易さ |
| API 連携の充実度 | ・API の基本機能 ・Webhook などのイベント連携機能 ・API・Webhook の制約 |
| 外部サービス連携 | ・外部システムとの標準連携機能 |
データの入出力機能は、他システムからのデータ移行、分析のためのデータ活用、他システムへのデータ移行など、様々なケースで重要になります。
また、API 連携や外部サービスの連携については、導入時には必要なくても、将来的に独自業務の要件に含まれるケースが多いため、確認することをお勧めします。
セキュリティと権限管理
ノーコードツールのセキュリティと権限管理は必須の評価ポイントです。特に、複数の部署やユーザーが利用するシステムでは、適切な情報アクセス制御が重要になります。
セキュリティと権限管理を評価する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
| 評価ポイント | 確認項目 |
|---|---|
| アクセス権限の細かさ | ・ユーザー/グループ単位の権限設定 ・画面/機能単位の権限設定 ・データレベルでのアクセス制御 |
| セキュリティ機能 | ・データの暗号化対応 ・認証機能の強度 |
| 監査 | ・操作ログの取得範囲 ・変更履歴の管理機能 |
アクセス権限では「誰が」「どの情報に」「どのようにアクセスできるか」を柔軟に設定できるか確認しましょう。
また、内部統制や監査対応の観点から、操作ログや変更履歴の管理機能も見逃せません。「誰が」「いつ」「どのようなデータを」「どう変更したか」を追跡できる機能は、不正操作の検知や問題発生時の原因究明に役立ちます。
コスト
ノーコードツールの費用を評価する際は、様々な費用要素と将来的なコスト変動を総合的に考慮することが重要です。
コストを評価する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
| 評価ポイント | 確認項目 |
|---|---|
| 費用体系 | ・初期費用の有無 ・月額/年額料金の構造 ・ユーザー数による課金方式 |
| 追加コストの発生条件 | ・データ容量による追加課金 ・API 利用量による課金の有無 ・高度な機能の別料金オプション |
| スケール時のコスト予測 | ・ユーザー増加時のコスト変化 ・データ量増加時のコスト変化 |
複数のツールを比較する際は、同じ条件で総コストを試算し、ツール導入による業務効率化や人的コスト削減なども含めた総合的な視点で評価しましょう。
評価を見定めるためのアクション
ノーコードツールを選定する際、前述の評価ポイントを実践的に検証するために役立つアクションは以下の通りです。
| 評価アクション | 内容 |
|---|---|
| 実際にデモ環境で操作 | 無料トライアルやデモ版で実際にツールを操作し、各評価ポイントの機能と使いやすさを検証 |
| 現場担当者による評価 | 実際にツールを使用する現場担当者から、直感的な操作性や学習コスト、使い勝手についてのフィードバックを収集 |
| 要件リストとの照合 | 現在必要な業務要件(優先度の高いもの)と、将来的な要件を洗い出し、各ツールがどの程度マッチするかを比較検証 |
| 第三者セカンドオピオンの導入 | 専門家や外部の第三者の意見を取り入れて、評価基準の妥当性やリスクを再確認 |
上記のアクションをバランスよく実施することで、カタログやウェブサイトでの説明だけでは判断できない実用性や適合性をより正確に評価しやすくなります。
中でも「実際にデモ環境で操作し、実際に触れてみる」ことは価値が非常に大きいです。操作感や直感性はもちろん、自社の業務を効率化する簡易システムを試作することで、ノーコードツールの適合性をより具体的に評価できるようになります。
また、業務の独自要件を実現するために必要な機能の解像度が高まるため、イメージが難しい将来を見据えた高度なカスタマイズ性能や方法についても、より踏み込んだ検討が進むでしょう。
このような背景から、多くのノーコードツールが提供している無料トライアルを積極的に活用することをお勧めします。
おわりに
本記事では、業務システム向けノーコードツール選定において、8 つの重要な評価ポイントについて解説しました。
| 評価ポイント | 概要 |
|---|---|
| 使いやすさ(UI/UX) | ・直感的な操作性 |
| 公式資料の充実度 | ・公式チュートリアルの充実度(特に初心者向け) ・関連資料の調べやすさ ・サンプルアプリやテンプレートの充実度 |
| モバイル対応性 | ・モバイル対応の有無 ・モバイル版とデスクトップ版の機能比較 |
| ノーコード機能の標準性能 | ・標準搭載のノーコード機能を用いた、システム構築力 / 汎用性 |
| 高度なカスタマイズ性能 / 方法 | ・複雑なビジネスロジックや UI の実現可能性 / 実現方法 |
| データ連携と拡張性 | ・インポート/エクスポート機能 ・API の充実度・使いやすさ ・外部システムとの連携の容易さ |
| セキュリティと権限管理 | ・アクセス権限の細やかさ ・暗号化などによるデータ保護 ・監査ログ |
| コスト | ・課金形態(初期費用、月額、ユーザー数課金など) ・追加コストの発生条件 ・スケール時のコスト予測 |
複数の評価ポイントを総合的に検討し、可能な限り実際に触れてみることが最適なノーコードツール選定の成功要因になります。また、現在の業務要件だけでなく将来の拡張性も考慮することで、長期的に活用できるツールを選べるでしょう。
本記事が、ノーコードツール選定の判断材料となり、最適なツール選択の足がかりとなれば幸いです。
この記事を書いた人

2016 年に旭化成株式会社に入社し、原料管理のシステムエンジニアとして従事。2019 年に株式会社キカガクに入社し、新規事業のソフトウェアエンジニア兼 C 向けコンテンツマーケティング責任者を担当。2024 年に、株式会社ファンムーブを設立。上場企業からスタートアップまで幅広く DX を支援している。
